

アンデルセンの『赤い靴』は教訓的で残酷な童話。でも、もし誰よりも綺麗な赤い靴を履いて踊れるのなら、死ぬまで踊り続けたっていい。そんな風に考えるのが女優の資格なのかもしれません。
誰かが共産主義のことを、百年の時をかけた壮大な実験だなどと述べていました。多くの社会主義国家が破綻している現在、事実上この「実験」は失敗に終わったとみるべきなのでしょうか。では残された自由主義の国々こそ、つまりアメリカやわが日本こそ、国家の理想なのでしょうか? 人類の歩むべき未来? 私にはわかりません。
ただし、百年前のロシア革命は、政治・経済から学問・芸術の分野にいたるあらゆる面で、世界中に甚大な影響を及ぼしたことは紛れもない事実です。多分そこには人々の「未来」が見えたのかもしれません。むろんここで社会主義のなんたるかとか、それが世界や日本に及ぼした影響の如何を語るには任が重すぎます。が、以下に、はじめての社会主義国家誕生の場に立ち会った数少ない日本人を、著作を通して紹介いたしましょう。
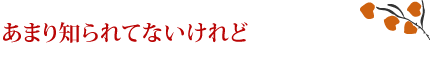
『露国革命記』(布施勝治 文雅堂 初版 大正7年11月25日)(写真1)
著者の布施はロシア革命の前後に、たまたま大阪毎日新聞の特派員としてペテルスブルグへ駐在していました。やがてロシアは革命騒動のまっただなかに。これはその渦中にいた著者のロシア革命実見記です。いま風に言えば迫真のルポルタージュ。布施は革命の成ったのちもしばらく現地に居残り、大阪朝日の中平亮と一緒に革命の指導者レーニンとの直接インタヴューを実現させました。さらにはスターリンのライバルで、レーニン後継の有力候補だったトロッキーとも数回にわたって面談するなど、ソ連の要人たちと親しくつきあい、彼らの言葉を日本に伝えています。
しかしながらこの布施の現地ルポ『露国革命記』がなにより画期なのは、ロシア革命を現場で見聞したノンフィクションの古典的名著とされてれる、ジョン・リードの『世界を震撼させた十日間』(1919年初版)よりも、僅かながら先行して刊行されていることなんです。
リードの『世界を~』がロシア革命を最初に紹介した実見記として世界的な名著とみなされ、幾度も版を重ねて今なお読みつがれているのに対し、残念ながらこの『露国革命記』や布施の名前は、同じ日本人でさえほとんど知る人はありません。内容については社会主義のシンパだったリードと立場の違いもあるのですが、動乱の渦中にいて、現地の新聞や周囲でおこる事件などを判断しつつ、刻々と移りゆく政治の趨勢を、時間と追いかけっこをするように描いていて、その点ではなかなか迫力があるのです。一番最初だからどうだ、ということでもないでしょうが、もしこれが英語の本として刊行されていたらと、つい思ってしまうのです。
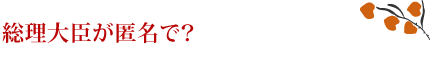
「快傑レーニン」(白雲楼学人 大日本雄弁会 大正13年2月10日)(写真2)
この匿名の著者は、のちの総理大臣・芦田均なんです。外交官として彼も大正7年の革命当時に、布施記者と同じくペテルスブルグに駐在していて、ロシア革命を現地で体験した数少ない日本人の一人となりました。上記はじめロシア革命については先行する書物がありますが、この本はレーニンの死をうけ、個人の伝記としてこの革命家を日本に紹介した最初の文献でしょう。またおそらく芦田にとっても、本名で刊行した『巴里会議後の欧州外交』(大12年)に次ぐ著作だったと記憶します。
なぜペンネームを使ったのかは知りませんが、本書の刊行時期に芦田はまだ外交官として活躍していたので、本名を出すのはまずかったのかもしれません。この本の巻頭には川上俊彦と伊藤正徳の序文が寄せられていますが、伊藤はその中で、「何故匿名で発行されねばならぬのか。日本の空気と制度との拘束であろう」と述べています。たぶん上層部から横やりが入ったのかな。
ちなみにこの川上俊彦は実業家ですが、日露戦争当時には外交官雇いとしてロシア関係の業務に携わっており旅順の戦役ののち、かの乃木・ステッセル両将軍の水師営の会見では通訳をつとめました。
♪旅順開城やくなりて、敵の将軍ステッセル~、乃木大将と会見の、ところはいずこ水師営~ですね。おっと、こんな歌、もう誰も知らないか(笑)。
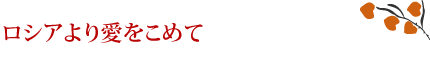
「子孫崇拝論」(小野俊一 黎明社 初版 大正13年6月15日)(写真3)
子孫崇拝とロシア革命が関係あるわけじゃあありません。実は本を紹介するのが目的ではないんです、問題は著者。小野は明治時代に財界で活躍した小野英二郎の長男として生まれます。動物学を勉強するためロシアに留学、そこでかの国の名門貴族の娘、アンナ・ブブノワと恋におち、両家の親族ともども大反対のなか結婚します。ところが折しもロシア革命が勃発、その混乱のまっただなか、駆け落ち同然に日本に戻ってきます。小野はその後にこの本を刊行し、いっときは社会運動家のような活動をするのですが、やがて父と同じく実業の道へすすみます。第二次大戦ののちはロシア文学翻訳家として過ごしました。
さて、この小野の結婚相手のアンナ・ブブノワこそ、わが国のバイオリン教育の礎を築いた小野アンナ女史。のちに息子の夭折が原因となり、小野と協議離婚するのですが、「小野」の姓はそのままで生活も共にしていたそうです。小野アンナはバイオリニストとして活躍するとともに、その門下には諏訪根自子、厳本真理、前橋汀子、潮田益子、浦川宜也など、日本を代表するバイオリニストが育ちました。
ここからは余談ですが、かのオノ・ヨーコも、この「小野」家の一族なんです。ブブノワ女史と血の繋がりはありませんが、小野俊一の姪にあたるんですね。ほら、ジョン・レノンが毎夏のように軽井沢で過ごしたって、聞いたことありませんか? パンを買いにいったり、いつもお気に入りの喫茶店で、珈琲を飲んで過ごしたり。あれ、実は小野家の別荘に来ていたんですって。

『ヅブロフスキー』(プウシユキン 山縣自然訳 聚英閣 大正10年5月20日)(写真4)
『黒パン』(-あるロシア革命の回想- 山縣自然 新時代社 1983年)
(写真5)
ブブノワさんの名前が出たところで、その繋がりの話をもうひとつ。この『黒パン』という本の序文の息子である山縣真澄氏の筆によれば、作者の山縣高七(自然)は遊学中にロシア革命を目撃した数少ない日本人の一人で、帰国後は東洋大学に学んだそうです。さらにブブノワに師事してロシア文学を専攻しました。しかしながらプーシキンの『ヅブロフスキー』(今は『ドゥブローフスキイ奇譚』角川文庫で知られます)を刊行した後は、文学を捨てて実業の道へ進み、やがて昭和20年5月、終戦の直前に49歳の若さで世を去ります。
そしてこの『黒パン』、大正10年当時に書かれた貴重な革命実見記なのですが、さまざまな経緯があって、結局60年のちに刊行されました。文壇にはほとんど足跡を残さなかった山縣です。結局この2冊が彼の刊行書のすべてなのでしょう。
ちなみにロシア語を学んだということで誤解されるといけないのですが、この山縣が師事したブブノワは、上記したバイオリニストの小川アンナです。彼女の姉のロシア文学で知られるワルワラ・ブブノワではありません。ロシア亡命時には、この姉のワルワラも一緒でした。ブブノア姉妹はともに日本文化に大きな足跡を残し、姉のワルワラは画家そしてロシア文学の教師として、後には早稲田や東京外語大の教師となります。たしか五木寛之のエッセイの中に彼女の名を見た記憶があります。五木のほかにも後藤明生、宮原昭夫、三木卓といった文学者も彼女に学んだんですよ。

写真1『露国革命記』
(布施勝治 文雅堂 初版
大正7年11月25日)
1917年の二月革命、十月革命を経て翌年のロシア出兵、ボルシェビキの単独政権樹立まで、まさにロシア革命の真っ最中に遭遇した新聞記者の革命実見記録。

写真2『快傑レーニン』
(白雲楼学人 大日本雄弁会
大正13年2月10日)
同年1月21日のレーニンの死をうけて、直後に刊行された伝記です。

写真3『子孫崇拝論』
(小野俊一 黎明社 初版
大正13年6月15日)
ロシアの名門貴族の娘アンナ・ブブノワと結婚とした著者は、社会運動家として活動したのち、ロシア文学翻訳家として活躍する。

写真4『ヅブロフスキー』
(プウシユキン 山縣自然訳 聚英閣
大正10年5月20日)
今ならばプーシキン著『ドゥブローフスキイ奇譚』で通じましょう。ほかに「お嬢さんの百姓娘」(「百姓令嬢」)を収録。

写真5『黒パン』
-あるロシア革命の回想- 山縣自然
新時代社 1983年)
若干二十歳の留学生がたまたま遭遇した革命体験記。前記した布施勝治も「某社通信員О氏」として登場し、山縣はいっとき彼の家に厄介になっていました。上記の翻訳や本書の執筆など、一時彼は文学を志すのですが、兄の死を転機として実業に進みました。

- ■ 2011年12月31日 第5回: ◆その五◆百年後の日本
- ■ 2011年12月10日 第4回: ◆その四◆ロシアより愛をこめて
- ■ 2011年09月15日 第3回: ◆その参◆『赤い靴』をはいて-女優たちの大正-
- ■ 2011年07月10日 第2回: ◆その弐◆恋する時代
- ■ 2011年06月01日 第1回: ◆その壱◆大正のカタチ
店名・品名・メニューなど、お好きな言葉で自由に検索できます。
- 音楽
- 楽器
- CD&レコード
- スタジオ・ライブハウス
- アミューズメント
- カラオケ
- ゲームセンター
- ネットカフェ・まんが喫茶
- 卓球場
